1975年、千葉生まれ。東京都立大学社会科学研究科博士課程修了。博士(社会人類学)。
人類学的視点を基盤として、パフォーミング・アーツやフォトグラフィーの持つ力と、社会的結合や新たな教育のあり方を接合する研究に取り組む。
日本南アジア学会常務理事、NPO法人FENICS理事、地域開発の実践と結びついて研究集団「生活文化研究フォーラム佐渡」を運営する。
共編著に『フィールド写真術』(古今書院)、『Jaisalmer:Life and Culture of the Indian Desert』(D.K.Printworld)、『インドを旅する55章』(明石書店、近日刊行)などがある。






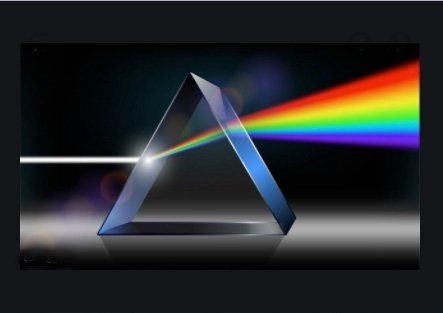






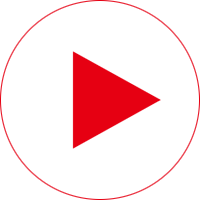

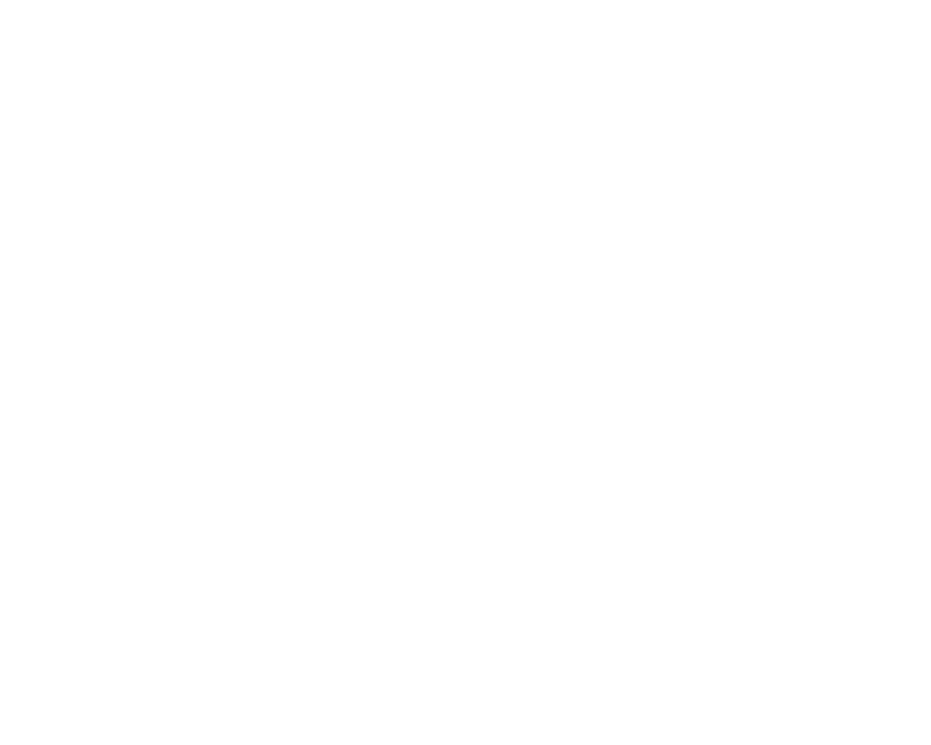
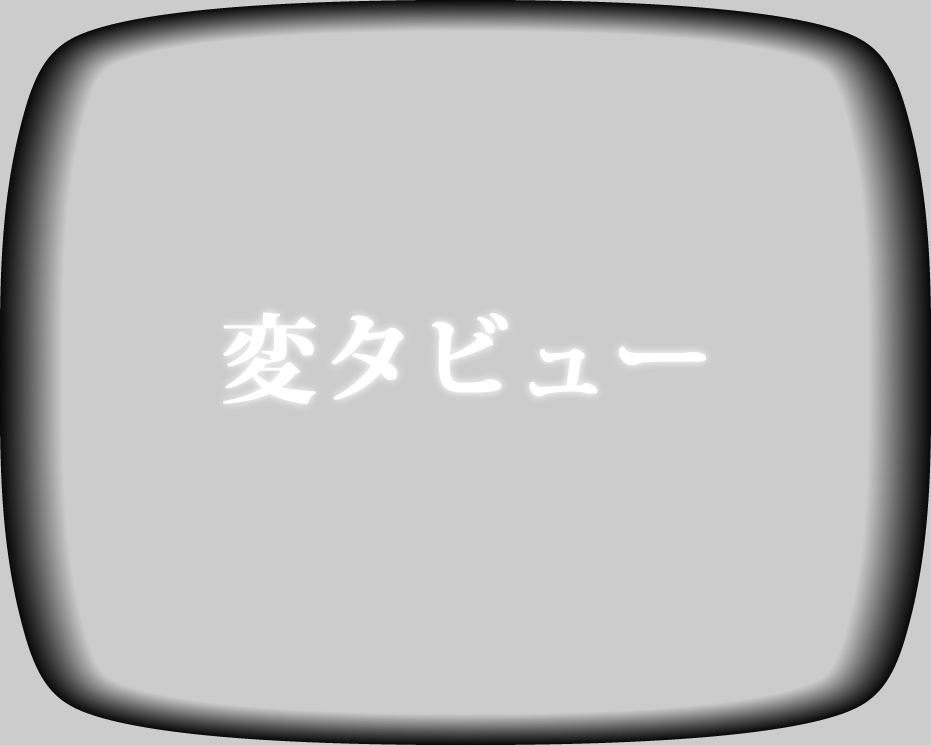
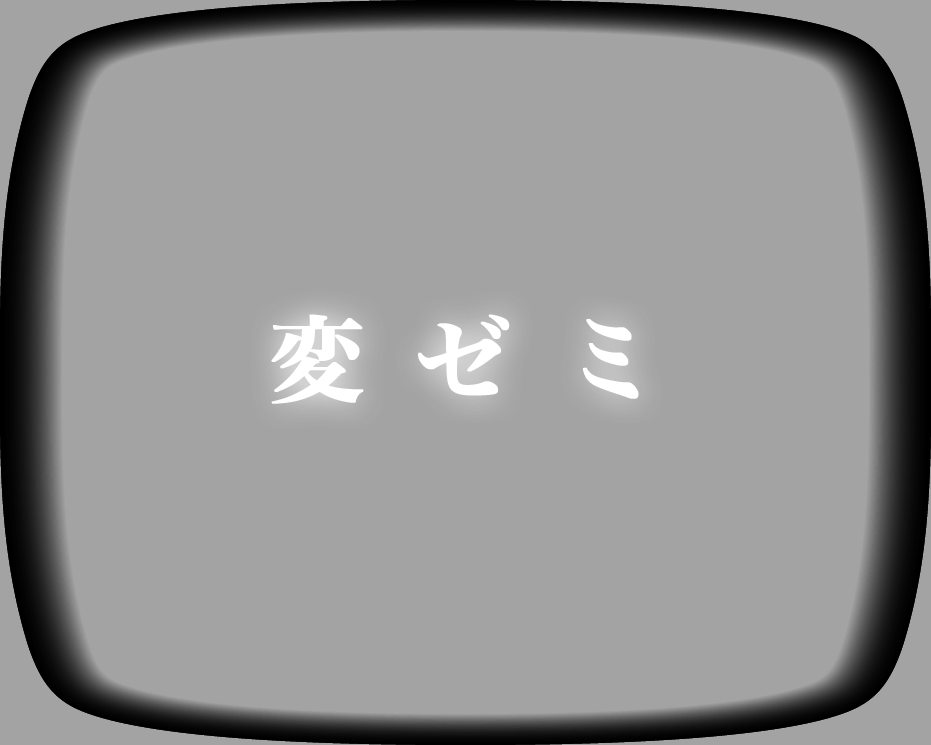
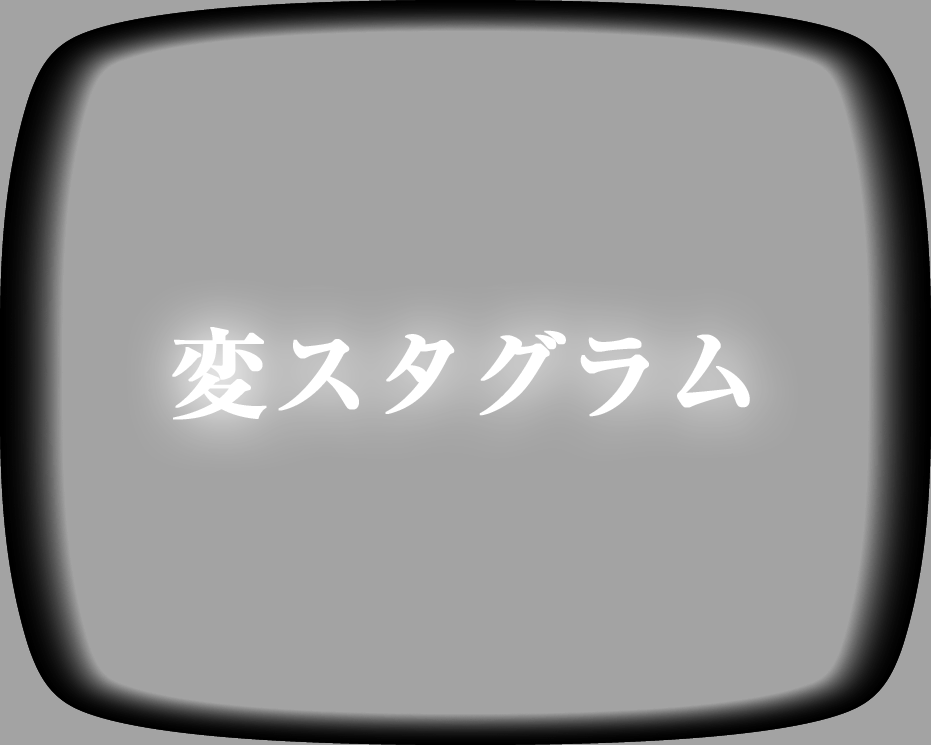
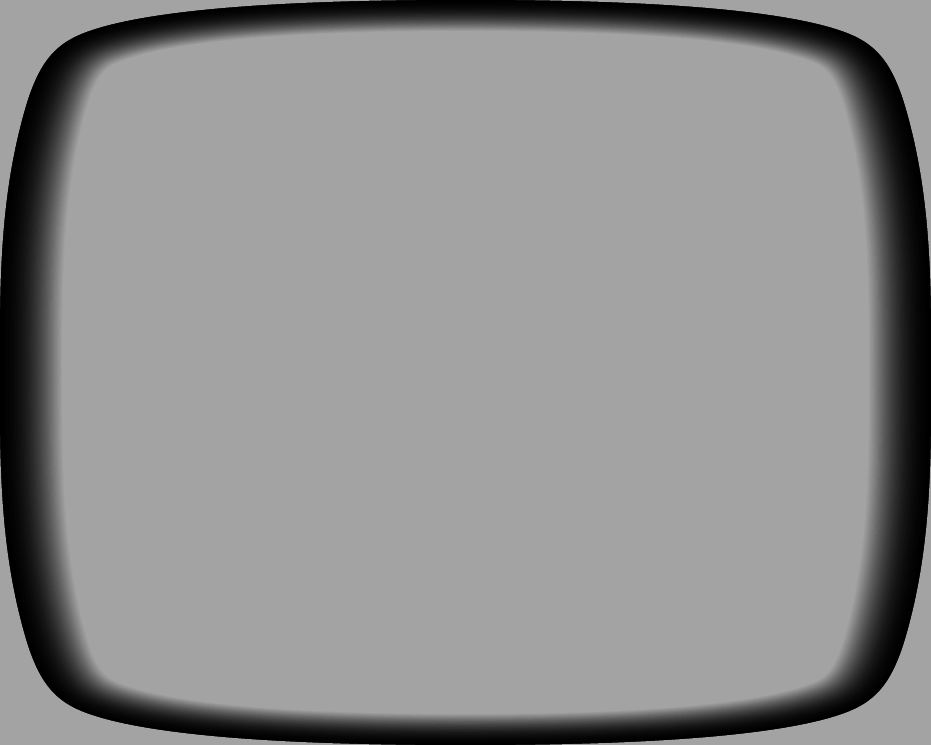
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)